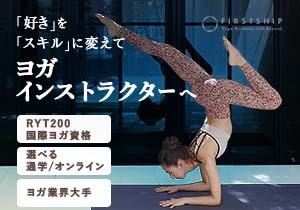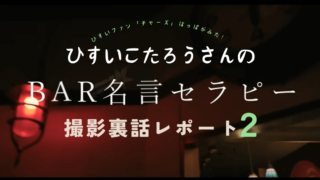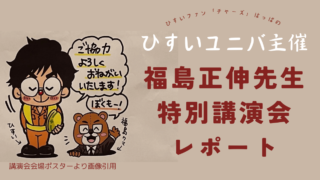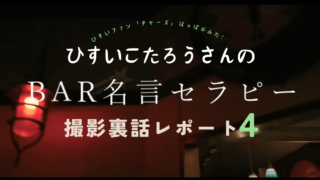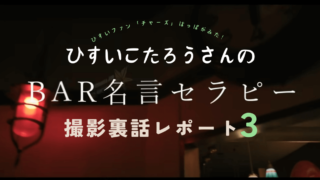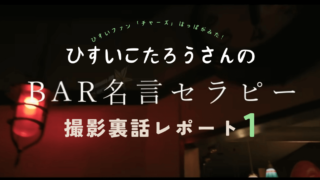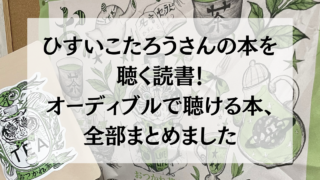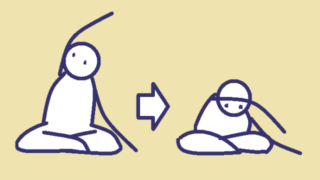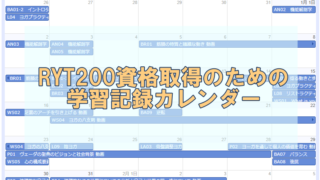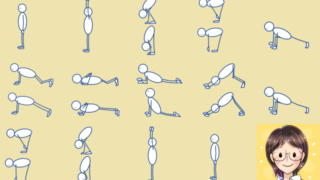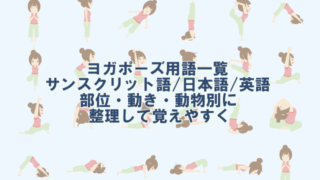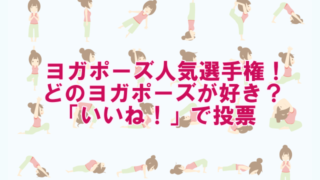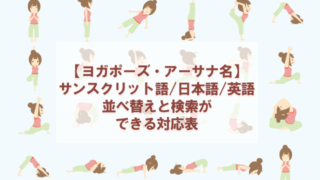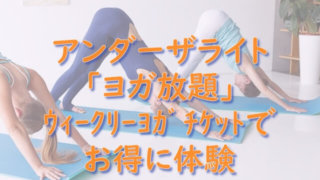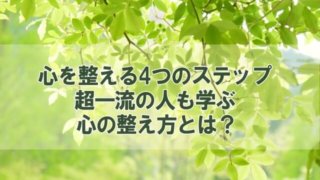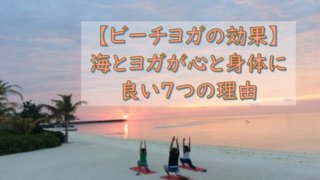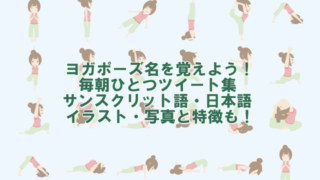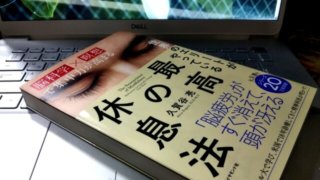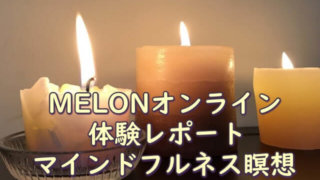Amazonプライムでたまたま目に留まった「聖なる呼吸:ヨガのルーツに出会う旅」
ヨガ初心者のドイツ人映画監督ヤン・シュミット=ガレ氏が、ヨガの起源を探るべくインドを訪ね、世界中に広まった現代ヨガの源流となる、南インドのティルマライ・クリシュナマチャリア師(1888~1989)の教えをたどったドキュメンタリー映画でした。
クリシュナマチャリア師の直弟子が、アシュタンガヨガの祖K・パタビジョイス師や、アイアンガーヨガの創始者アイアンガー師なのです。
この映画には、1930年代のクリシュナマチャリア師自身や、弟子たち、子どもたちの貴重なヨガの実演映像や、取材当時まだ存命だったパタビジョイス師やアイアンガー師が監督のガレ氏に直接ヨガ指導する様子の映像がふんだんに入っています。
貴重な映像や南インドの美しい風景がちりばめられた、ヨガを学ぶモチベーションが確実にアップする、この映画の魅力を詳しく紹介します。
私は視聴1度めはヨガの予備知識が足りず映像の価値がわかりませんでした。
2度目に、基本的なヨガの名前やヨガ哲学の知識を得て観たときには、すごい映画だったとわかりました。
クリシュナマチャリア師がいなかったら、今のように私たちがヨガを知ることはなかったかもしれません。
古代の文献からヨガを掘り起こし、広く世に出してくれた師に感謝します。
T・クリシュナマチャリア師のヨガ指導の軌跡
ムチュクンテという南インドの村の映像から、映画が始まります。
この監督のヤン・シュミット=ガレ氏は、ヨガを体験して心と身体の融合を感じ、アーサナ(ヨガのポーズ)の起源や、ヨガの歴史について知りたくなったのだそうです。
そしてインドに出向いてクリシュナマチャリア師をめぐる人々を取材し、この映画が生まれました。
クリシュナマチャリア師の弟子や子どもは次のような方々です。
このうち、☆印の方に直接取材して映画が師の軌跡をたどります。
弟子
1927~
パタビジョイス(最初の弟子)☆
1934~
アイアンガー (義理の弟)☆
1947~
I・デーヴィー(アメリカにヨガをもたらす)
S・ラーマスヴァーミー
A・G・モーハン
6人の子どもたち
長女 プンダリーカヴァッリー☆
次女 アラメール☆
長男 シリーニヴァーサン
次男 デーシカチャル
三男 シリーバーシャム☆
三女 シュバ☆
クリシュナマチャリア師はサンスクリット大学の教授でヨガの実践と哲学を教えていましたが、マイソール藩王のクリシュナラージャ4世の招聘によって、1933~1935年の間、王宮のヨガ道場で王や王族のヨガ指導にあたっていました。
当時のヨガの目的は魂の追求で、無償で学べるものだったそうです。
近隣の都市からヨガ講師として招かれたときは、講演と実演を行い実演を行う弟子が数名同行し、頼まれればその地の残りヨガ指導者となったそうです。
クリシュナマチャリア師と1930年代のヨガ実演の貴重な映像の数々
この映画には、1930年代の記録映像がたくさんちりばめられています。
クリシュナマチャリア自身、弟子たち、6人の子どもたち、マイソール藩王(マハラジャ)や宮殿、へび使いなど、当時の様子をうかがい知ることができる次のようなモノクロの貴重な映像を観ることができました。
記録映像「偉大なる賢人 ティルマライ・クリシュナマチャリア 日常の練習」
インドのマイソールで、1930年代に世界に広まった現代ヨガのルーツを作ったクリシュナマチャリア師がヨガをする映像です。
記録映像「クリシュナマチャリアの優秀な弟子 B・K・S・アイアンガー」
アイアンガーヨガの創始者のアイアンガー師が若かりし頃の(おそらく10代)、ヨガの実演映像が収められています。
記録映像「藩王の御前での実演」
マハラジャの宮殿と宮殿の人々、宮殿の庭庭に設えられた舞台上には、クリシュナマチャリア師とヨガの実演をする5人の弟子(子どもも?)の映像が残っています。
記録映像「クリシュナマチャリアの娘 プンダリーカヴァッリーとアラメール」
幼い2人の姉妹のヨガ映像が残っていました。師から指導されたヨガの基本的な動きを実演する姉妹の様子です。
記録映像「クリシュナマチャリアの妻ナマギリ」
1930年代のインドでヨガを学べたのは限られた人でしたが、クリシュナマチャリア師はヨガは万人のものと壁を取り払い、女性にも学ぶ権利があると女性にヨガを学ぶ機会を与えたのだそうです。この映像では彼の奥さんがヨガを行う様子が映っています。
記録映像「へび使い」
ヨガではありませんが、コブラをかごから出して笛で操る当時のへび使いの映像です。
記録映像「ブッダ・アーサナ」
高度なヨガのアーサナを弟子が実演する映像です。
記録映像「クリシュナマチャリア ナウリ・クリヤーの実演」
呼吸法を実践するクリシュナマチャリア師のお腹の映像が残っています。
記録映像「ヨガの師 クリシュナマチャリア 87歳」
クリシュナマチャリア師87歳の映像も残っていました。本を読み、食事をし、小鳥に餌を与えます。
アシュタンガヨガの祖K・パタビジョイス師の映像から
この映画の撮影開始当時、K・パタビジョイスも健在で、椅子に腰かけて、大勢の外国人の生徒に太陽礼拝をガイドし指導している様子が撮影されました。
パタビジョイス師がクリシュナマチャリア師について語る
パタビジョイス師が師について語る様子も収められています。
ヨガを知る人がほとんどいない当時のヨガ教育では、クリシュナマチャリア師は、古代の文献「ヨーガ・コルンタ」という文献から学び、弟子にヨガを教えていたそうです。
当時撮られた集合写真には、クリシュナマチャリア師とまだ子供だったパタビジョイス師を含む大勢の弟子が映っていました。
パタビジョイス師から太陽礼拝を指導される監督のガレ氏
ガレ氏自身が、パタビジョイス師から太陽礼拝を指導していただいていました。指導の後、「始めるまえより呼吸が良くなった」とパタビジョイス師はガレ氏を褒めます。
また、あぐらを組むパドマ・アーサナができないガレ氏に、師は「練習すればその日はくる」と語ります。
その日とは「ハタ・ヨーガ・プラディーピカー」第1章の最後に「年老いた人や病気の人でも”練習でヨガを完璧にできるようになる”」と書かれているのだそうです。
パタビジョイス師亡きあとの回想
この映画を作成中、ガレ氏らがプネーにいるときに、パタビジョイス師が亡くなり孫のシャラートジョイス氏が跡継ぎになりました。
アシュタンガヨガについてパタビジョイス師は語っていました。
「アシュタンガヨガの第1の目的は、身体を浄化させること、そして心の動きを滅しコントロールしして完全なる心の制御を目指します。
まずはアーサナの練習、身体が制御できれば心も制御につながります。到達には長年の練習が必要ですがいつかコントロールできるようになる、それが本当のヨガなのです。」と語っています。
アイアンガーヨガの祖B・K・Sアイアンガー師の映像から
1960年代に渡欧し同世代で最も有名なヨガ指導者になったアイアンガー師。
アイアンガー師がヨガを学んでいた頃は、ヨガは実践が軽視されヨガ哲学が中心、さらに、ヨガは心を病んだ人行うものだという偏見があったのだそうです。
アイアンガー師がクリシュナマチャリア師について語る
師であり義兄であるクリシュナマチャリア師のことをアイアンガー師は批判的に語ります。
クリシュナマチャリア師は、義弟であるアイアンガー師には厳しくあたったため、アイアンガー師はプネーでヨガの指導をするよう命じられ、師から離れられた時、自由になれて嬉しかったといいます。
アイアンガー師は、師にアーサナのやり方を詳しく教えてもらえず無理強いされ、完治に2年もかかる太ももの肉離れをしたのだとのこと。2人の間に確執があったことがうかがわれます。
痛みから体の使い方とケガの理由を探ったアイアンガー師は、パタビジョイス師とは異なるヨガメソッドを作り出しました。
アイアンガーヨガは、長くて30分間もアーサナを維持し、経験が浅かったり故障歴があったりしても様々な道具類を使うことで、ヨガの効果を最大限に引きだします。 そのアイアンガーヨガの練習風景は、一種独特のものです。
ガレ氏がアーサナをただすのに鏡を使っていたのかと尋ねると、アイアンガー師は、鏡も買えない当時、自分と対話しアーサナを正すためには左右の感覚を比較し考える、どのように働かせば正しい感覚になるか知性を働かせていたと答えます。
アイアンガー師の指導映像
アイアンガー師の指導映像では、アーサナのために知性を働かせるということがよくわかります。
「ひねるときは背骨を軸にする、体でなく軸を回す、軸の回転で」と指導するアイアンガー師。
上向きの弓のポーズをとる弟子に、「裏側を使って前側を持ち上げる、前側は力をぬき かかとは上、足首は下げる、筋肉の力は使わず、のどの力を抜く」などと体の使い方を丁寧に指導していく様子が印象的でした。
天井からの紐に体を預けていたり、頭で立つアーサナだったり。静かな中で大勢の弟子たちが学んでいました。
アイアンガー師からシールシャ・アーサナの指導をうけるガレ氏
頭で立つ、シールシャ・アーサナの、バランスの取り方が知りたいというガレ氏。
アイアンガー師は詳しく丁寧に教えます。
ここは見どころなのでぜひ、実際の映像を見てください。
アイアンガーヨガは知性を働かせ、体の全体を使った練習で、部分的ではなく体全体を使った全体論だといいます。アーサナの維持がすべてに作用し、意識から皮膚、皮膚から意識へと全体論的練習だというアイアンガー師の指導は、ヨガを学ぶ方なら一見の価値があります。
クリシュナマチャリア師の子どもたちへのインタビュー
ヨガの指導者三男のシリーバーシャム氏
美しい離宮で撮影された、ヨガの指導者三男のシリーバーシャム氏へのインタビュー。
「ヨーガ・マカランダ」というクリシュナマチャリア師の著書も紹介されています。
新たなヨガの方式が、王の意向がきっかけで生まれたことがわかります。
当時、イギリスとの緊張が高まっていたインドの情勢の中、ヨガの動きを早く高度にしてひとつのアーサナ(ポーズ)から次のアーサナへと次々に動くその方式は、王族の男子が身軽に動く方法を学ぶために作った武術を習う感覚のヨガで、インド哲学のミーマンサー学派の用語から「ヴィンヤサ・クラマ」と名付けられました。
サマスティティという直立の姿勢のポーズから次々とアーサナをとり直立姿勢にもどります。
ガレ氏が三男氏にアーサナの起源についてインタビューすると、当時多くのアーサナを知るアーサナはほとんどおらず、クリシュナマチャリア師が古代の叙事詩「マハーバーラタ」などに登場する多くのアーサナを、整理し指導していたのだろう、アーサナの出典を教えてくれたと語ります。
長女のプンダリーカヴァッリーさんと次女のアラメールさん
クリシュナマチャリア師の当時の生活を長女が語ります。
クリシュナマチャリア師は、朝起きると6人の子どもたちに6時から8時半までヨガを教え、朝食、11時から11時半まで呼吸法、昼食、午後2時以降は弟子たちに、古代の叙事詩「マハーバーラタ」などを教え、自分の研究時間、3時以降はまたヨガの理論と実践を指導、5時から8時は道場でヨガを教え、帰宅後は古代の書物を読む、という生活だったそうです。
クリシュナマチャリア師は「知識は財産であり宝だ」と考えていた、「知識は誰にも奪えないから」、とマハラジャ・サンスクリット大学で語るのは次女のアラメールさんです。
お二人の幼いころの映像が貴重な資料として映画で紹介されています。
クリシュナマチャリア師の「命をつなぐヨガ」
クリシュナマチャリア師は学者や司祭が属するバラモン階級の出身でした。
六派哲学のすべてを修め、ヒマラヤの洞窟に住む、ラーマモーハン・ブラフマチャリアのから3000ものアーサナと呼吸法プラーナーヤーマを学び、大変優秀な方だったとのこと。
体の機能を制御して心臓を2分間停止できたため、イギリスの科学者が調べにきたそうです。ヨガの起源やインドの神秘とかかわりがありそうです。
「ヨガとは集中することです。サマーディとは深い集中のこと、アーサナを行いながら息を吐くときはアーサナとその瞬間に集中する、それが心と身体との一体化につながる」と父から教わったというアラメールさん。
「練習に集中しなさい、自分の魂に集中すべき」「集中しなければ、気づきは得られない」というクリシュナマチャリア師は、人々から厳しい人だといわれていたと娘たちは語ります。
三男によるクリシュナマチャリア師の指導法の実演
マイソールのサンスクリット大学で、三男がクリシュナマチャリア師の指導法を見せてくれました。
小さな子供への指導法法の実演
セッションは祈りから始まります。叙事詩「バガヴァド・ギーター」讃歌の詠唱です。
小さな子供のスプタ・パルヴァタ・アーサナやマツヤ・アーサナの練習が実演されます。
クリシュナマチャリア師は、子どもに対して1つのアーサナを教えるとき、時間を区切るために「ガーヤトリーマントラ」などの詠唱を行っていたそうです。
サンスクリット語学者へのヨガの指導方法実演
サンスクリット語学者にヨガを指導するときには、古代の聖典を用いてヨガを教えていました。
アーサナを行っていても集中できないことがあるため、心の中で「ガーヤトリー」を詠唱しなさい、という風に。アーサナごとに特定のマントラを唱えさせ集中を深めさせたといいます。
三女によるクリシュナマチャリア師から教わったヨガの実演
サンスクリット大学で三女のシュバがクリシュナマチャリア師から教わったヨガを実演してくれた映像です。
今も毎朝行っているヨガの実践。師は、「呼吸と動きを同調させなくてはヨガではない、深く集中しながら呼吸と動きを連動させるのだ」と教えたそうです。
ガレ氏とアレックス氏が語るヨガの魅力
ガレ氏がヨガの魅力について語ります。
ジョギングや山登りで幸福感やアイデアが浮かぶ脳の活性化の状態が、ヨガでも同じようになる。「ヨガで意識がはっきりし、脳が活性化する」とガレ氏。
アレックス氏は、聖賢のパタンジャリの言葉で「ヨガとは心の動きを滅すること」を引きます。
「ヨガをしている間、気持ちが落ち着いて安定し、意識がクリアになっていく、せわしない心に静けさがやってくる」というアレックス氏。
ガレ氏はヨガをすれば気分が良くなることがわかっているがもろもろの家事で練習を後回しにしてしまうとのこと。
インド独立後のクリシュナマチャリア師
1947年のインド独立後、州の財政難からヨガ道場は閉鎖、数年後チェンナイの実業家に呼び寄せられ、チェンナイで治療や個人指導を行ったそうです。
チェンナイでもヨガを広めようと息子たちに実演させていたそうです。その後も次男、三男はヨガを続けたそうです。
ヴィヴェーカーナンダ大学
チェンナイの大学でヨガが科目になり、ヨガの3つの目的
1つ目:健康な体
2つ目:健全な心
3つ目:集中力を得ること
を教えていたそうです。
命をつなぐヨガ
このころには、クリシュナマチャリア師の指導法もアーサナを維持する、呼吸がより重要な方法に変わっていたことがわかります。
当時、師から直接ヨガを教わった、実業家のK・ダース氏に取材しています。
大学でのヨガ指導では、最初は呼吸法のプラーナーヤーマ、次がアーサナを教えたとのこと。
1つのアーサナを覚えると、翌週には1つ増え、完璧に習得したら次のアーサナ。
1つのアーサナは2~3分維持していました。。
呼吸法はきつい練習だったそうですが、集中力が高まり、「ヨガの後は疲れず元気になるところが他の運動とは違うところだ」とダース氏は語ります。
ヨガのアーサナの起源?
アーサナの起源かもしれないと三男シリーバーシャム氏がガレ氏を連れてきたのは、小さな寺院、クリシュナ寺院の神様の名前は「ヨガ・ナラスィムハ」
ヒンドゥー教の神話に初めて出てきたアーサナの絵が壁に描かれています。
神話やヴェーダの時代、神の取る姿勢がアーサナと言われていたそうで、最初にアーサナをしたのが、瞑想をする神の絵でした。
「座って呼吸をする神」ヨガと同じです。この神が起源なのか?とガレ氏。
クリシュナマチャリア師の教えていた「命をつなぐヨガ」をガレ氏が実践
三男シリーバーシャムから、クリシュナマチャリア師が教えていた「命をつなぐヨガ」の4種の呼吸と8種のアーサナの指導を受け、ガレ氏が集中を学びます。
マツヤ・アーサナ(魚のポーズ)
ブジャンガ・アーサナ(コブラのポーズ)
サルヴァーンガ・アーサナ(ショルダースタンド)
ハラサナ(鋤のポーズ)
パシチモーッターナ・アーサナ(着席前屈)
⇒集中が不快状態になり心が完全に平穏に。
三男シリーバーシャム氏は、インドでは神がいかなる時も心の中にいるが、欧米では違うので父は信仰心を押し付けたくなかったはず、クリシュナマチャリア師はそのために私たちが神を渇望する思いを誰もが感じられる方法を探ったのだろうといいます。
ヨガで集中が深い状態に、心が完全に平穏な状態に。精神に集中し練習を終える。
宗教は関係なく、魂がある場所を考える。
精神と直結した平穏な心をもって自己のスピリチュアルな人生が見える瞬間がある、そして練習で長い人生の生き方が身に付きます。
と語ります。
この映画の製作によって、アーサナの由来やヨガの歴史と起源となる時代について知ろうとしたガレ氏。
他にも重要なことを学んでいました。
「アーサナは集中し、正しく呼吸をすれば効果を発揮する、それがヨガなのだ」と学んだのだそうです。
聖なる呼吸 ヨガのルーツに出会う旅 まとめ
自分がふだん行っているヨガのルーツ、源流を、その道のマスターオブマスターの映像で学ぶことができるこの映画に出会えてよかったです。
クリシュナマチャリア師の威厳のある風貌と、弟子たちの実演が目に焼き付きました。
100年近く前の映像が残っていたことに心から感謝します。
この映画を観ると、ヨガの練習、呼吸の練習、瞑想の練習のモチベーションが上がる映画、どうぞ一度ご覧になってください。
今ならAmazonプライムで無料で観られます。
Amazonプライム未加入の方も「Amazonプライム無料体験」で観ることができます。
⇒ 「聖なる呼吸:ヨガのルーツに出会う旅」を観る。