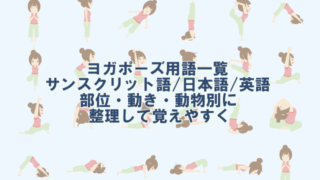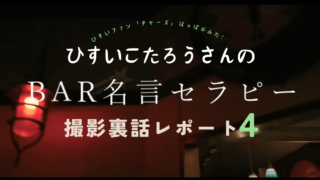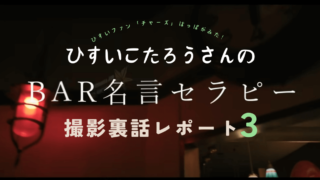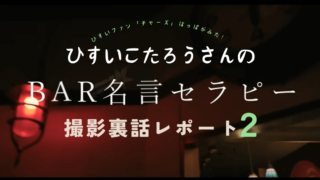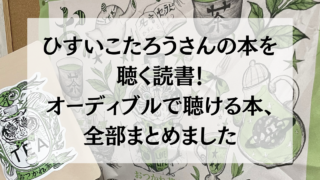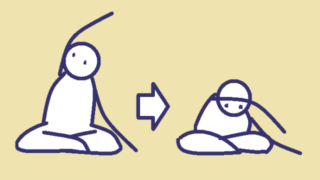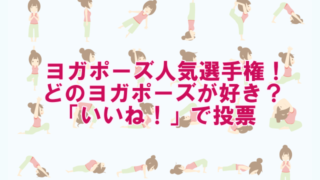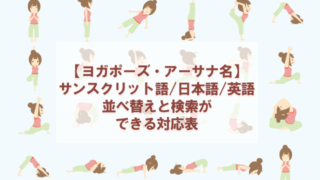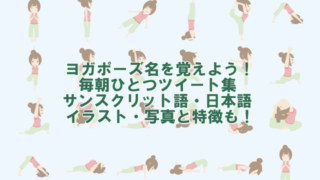上橋菜穂子さんの書かれた「精霊の守り人」に始まる「守り人」シリーズ。
ファンタジーでありながら児童文学の枠を超えて、幅広い世代に支持されるベストセラーです。
ラジオドラマ、アニメ、漫画、ドラマ化とたくさんのメディアに展開され、世界8か国語に翻訳され世界中で読まれる本となっています。
このシリーズは図書館員をしていた時に読みました。
30代の大人の女性の槍使いバルサが、まだ少年の皇太子チャグムの用心棒となるところから始まる壮大なスケールのシリーズです。次へ次へと引き込まれてシリーズ全巻を堪能しました。
ちょうど同時期、図書館で働きながら通信教育で司書資格を取得していました。
その受講科目の中の「児童サービス論」という授業のレポートで児童文学の中から一つのシリーズを選び、その全巻を読んで作品論を書くというものがありました。
私は「守り人」シリーズを選び、特に2作目の「闇の守り人」を読み込んで作品論を書きました。
 「闇の守り人」レポートのために読み込んだ形跡が残る
「闇の守り人」レポートのために読み込んだ形跡が残る通信制で司書資格を取ったときの記録の記事を作成中ですが、参考記事として先にこの「児童サービス論」の課題レポートのひとつを公開しておきます。
稚拙なものではありますが、通信制司書資格の課題の難易度の参考にしてください。
※ブログ用に見やすさのため、改行、タグ、写真等を追加してあります。
司書資格「児童サービス論」課題 児童文学シリーズを読んでの作品論レポート
「槍舞い」で突きぬけられた心の境界線-『闇の守り人』より-
1. はじめに
主人公のバルサとその養父ジグロ、そしてヒョウル<闇の守り人>たちの、カンバル王ログサムの陰謀に翻弄された人生と、それによって心に負った傷がどのようにして癒され、清められていったのかに、この作品の中で最も興味を引かれた。
『闇の守り人』では、バルサが心の古傷に向き合うためにカンバルへ戻ることを決意した時に、こう書かれている。「身体についた傷は、時が経てば癒える。だが、心の底についた傷は、忘れようとすればするほど、深くなっていくものだ。それを癒す方法はただひとつ。――きちんと、その傷を見つめるしかない。」*1
この作品のテーマは、「傷ついた心」の状態から「癒」された状態へと心の境界線を越えていく過程であると考える。特にその「癒し」に至るクライマックスは「槍舞い」という儀式の中に丁寧に描写されている。そこで「槍舞い」の持つ意義を検証し、「槍舞い」の儀式の間のバルサ、ジグロ、そして<闇の守り人>ヒョウルの心の状態を解析した。
2. バルサの心・ジグロの心・ヒョウルの心
『闇の守り人』の登場人物の中で、傷ついた心をもち「槍舞い」の儀式を通して心の状態が変化していくのは、バルサだけではない。すでに死者であるバルサの養父ジグロや<闇の守り人>ヒョウルたちもまたそうである。
バルサの養父ジグロは、カンバル王ログサムの陰謀にまきこまれたバルサの実父に頼まれ、<王の槍>と呼ばれる王を護る9人の武人の中でも最高の槍の使い手としての名誉も地位も捨てて、バルサを連れ隣国へ逃亡した。そして王が次々と放つ刺客たち、かつての同僚の王の槍8人全員を殺し続けた。バルサを守るという友との約束、バルサさえいなければという気持ち、友人を殺さなければならない状況の間でひきさかれるような思いを味わい続け、最期は病で苦しみながら亡くなったのである。
また、ヒョウルとは、「一命を賭しても<山の王>の秘儀をまもることを誓い、死すれば山の底にかえって、山の王の闇をまもるヒョウル<闇の守り人>となる<王の槍>」*2たちである。槍舞いの儀式の場でバルサたちを向かえたヒョウルは、王の命令でかつての友人ジグロを討ちに向かい、ジグロに討たれて死んでいった王の槍たちであった。無念を抱えたまま、人生なかばで選ぶ道のない死を遂げていった死者たちなのである。
そしてバルサは、幼い娘の頃から「何をしたわけでもないのに、父親を殺され、寒くてひもじい思いをしながら旅をつづけなくちゃならないんだって、いつも腹がたって」*3 いた。理不尽で「むごい運命をかってにせおわされ」*4、30歳を過ぎる現在に至るまで女用心棒として生きてきたのだ。
またバルサは、養父ジグロのことを「ただ父の親友だったってことだけでこんなにひどい人生をおわされてしまった、わたしよりずっと不幸な人」*5と、自分のせいで人生を犠牲にしてしまった人としてとらえ、ジグロに対して心にしこりを持ち続けている。バルサの命を守るために刺客であるかつての同僚たちを殺すたびにジグロが感じた哀しみは、バルサにも深い心の傷を与えてきたのだ。
ジグロが死んで6年経ち、バルサはカンバルに帰り古傷に向き合うことで、「わたしの中のジグロの亡霊が消えていくだろう」*6と考える。ようやく「どうにもならない自分の気持ちに、とことんつきあってみよう。そしてつきぬけたさきになにがあるのか、みてみよう」*7と、今まで避けてきた自分の気持ちと過去に対峙するのである。
3. 「喪の仕事」
心理療法の世界では、「失った対象との間でおきている気持ちの整理を心の中でなしていく」*8ことを「喪」の仕事と呼んでいる。バルサは、ジグロに対して抱く複雑な感情を整理しきれないまま6年間生きてきたと考えられ、未だ喪の仕事が完了していないといえる。また、自分の人生を認められない気持ちのまま、向けるあてのない怒りを心の奥底に抱えて生きている。
バルサは、故郷カンバルにおいて、唯一の肉親である叔母のユーカと再開し、自分とジグロのたどってきたこれまでの人生を語った。「叔母に話したことで、なんだか心のおりが洗い流されてしまったような気がしていた。さっき感じた激しい怒りは、埋み火の熾のようなものに変わり、その上をあきらめという灰がおおっていくのを感じていた」*9 この表現から、自分しか知らなかった真実を叔母に知ってもらい過去を共有することで、心の重荷を下ろしたバルサの心情がうかがえる。
4. 「癒し」の条件 ――心の回復のプロセスから
傷ついた心の回復の過程のひとつのモデルとして、精神科医キューブラー・ロスの言う、あらゆる種類の喪失に悩む人たちの心理プロセスを挙げておく。
はじめに起こるのはショックと否定、怒りと憤り、嘆きと苦痛である。つぎに神との取引がはじまる。意気消沈し、「なせこのわたしが?」と問いはじめる。そしてついには他者から距離を置き、自己のなかにひきこもるようになる。その段階をへて、うまくいけば、やすらぎと受容の段階がおとずれる(悲嘆と怒りが表現できないときは、受容ではなく断念になる)*10ここでは、悲嘆や怒りの表現が、やすらぎの段階にいたる必要条件になるということが重要であると考える。膿んだ傷から膿みをださなくてはかさぶたができないように、怒りや恨みなどの心の奥底に抑え込められた感情を表に出すことが、心の癒しには必要なのである。
このことはバルサだけでなく、死者としてヒョウルとなったジグロや<王の槍>たちにも言えるであろう。死者であるヒョウルの場合には、以下のように「穢れてしまったヒョウル<闇の守り人>を弔うのに、これほどふさわしい者もほかには、おるまい。な、祈っていよう。……バルサが、みごと彼らを清め、弔ってくれることを」*11と、「傷ついた心」は「穢れ」、「癒された心」は「清め」と、言い換えられていると考える。
つまり、バルサを癒し、ジグロやヒョウルを清め弔うには、悲嘆や怒りの表現が必要となるのである。
「死」について考える参考資料 エリザベス・キューブラー・ロスの著書
5. 「槍舞い」が心を開かせるのは何故か
「槍舞い」では、「ヒョウル<闇の守り人>と槍舞いをまって心をひらかせること」*12が必要とされる。それは、いかにして可能となるのであろうか。
「槍舞い」が行われる儀式場の闇の中では、人の心が読まれ、口に出さなくとも、人の思いがその場にいるもの全ての者の心にひびいてくる、とされている。心に思うだけで伝えることができるのである。言い換えれば、心に思うことは伝えたくなくても伝わってしまうのである。
さらに、槍舞いは無心の技とされており、「<槍舞い>は、素裸の、むきだしの魂でしか舞えない舞だ。その舞を舞いながら、ヒョウルは、<舞い手>に思いのすべてをぶつける。」*13とされる。考えながら舞うあるいは戦えるものではなく、体にしみこんだ動きだけが次々と繰り出されるのである。
こうしたことから、集中して槍を繰り出し槍舞いを舞ううちに、舞い手にしてもヒョウルにしても、心の奥にしまいこんで封印していた感情が表にでてくるのだろうと考えられる。「ヒョウルの思いなのか、<舞い手>の思いなのか、わからなくなるほど、近々と魂をつなぎあって」*14舞うことで、伝え合うことなく死に別れたもの同士が本心を伝えあい、心のわだかまりを全て流すことができるのである。
だからこそ、心の中の膿みが流せ、傷が癒え始めるのであろう。そして、ヒョウルは、心からの別れの言葉を伝えてあの世へと旅立つのである。舞い手は、「槍舞い」によってヒョウルを弔うことができたことになるのだ。
6. 「槍舞い」で心の境界線を越える瞬間
「槍舞い」が心を開かせ、バルサ、ジグロ、そしてヒョウルが、「傷ついた心」から「癒し」へと、心の境界線を越えていく様子は以下のように表現されている。
槍舞いが始まると、バルサは、「槍の攻撃の、ひとつ、ひとつから、噴きだすような感情を感じるようになった」*15。死者たちが、生前、心の中に押さえ込んできたものが、槍舞いによって無心に舞うことで心の奥底から感情として噴きだしてきたのだといえよう。
バルサの「傷口から、ジグロの、おさえきれぬ憎しみがしみこんできた」*16。「バルサさえいなければ」*17というジグロの本心が、バルサに伝わったのだ。
「八人のヒョウル<闇の守り人>からも、憎しみの波が押しよせてきた」*18。ヒョウル、かつての王の槍たちも、やはり「おまえさえ、いなければ」*19とバルサを憎んでいた。
「骨をかむような痛みが、バルサの胸の底に沈んだ」*20後、いよいよ、バルサの押さえ込まれてきた心の内が表現される。
「何かが心の中に顔をだした。――それは、うずくような、激しい怒りだった」*21
「それは、むきだしに怒りだった。心の底にかくしてきた――自分にさて、かくしてきた怒りが、おさえようもなく噴きだしてきて」*22
「あんたが、わたしをうらんでいるのを感じていた。――ずっと、感じていたんだ」*23
「たまらない、痛みだったんだ!(中略)けっして消えない痛みだったんだ」*24
「ずっと、その重荷を負って、生きてきたんだ!」*25ぶつけるあてのなかった押さえ切れない怒りが、初めて吐き出されたのである。
バルサは「自分を見つめるジグロの目を、見たような気がした」*26そして、「おれを殺せ。そして、怒りのむこう側へ突きぬけろ……」*27と、ジグロの心の声を聞くのである。
この瞬間、バルサは「傷ついた心」の状態から「癒し」へと、心の境界線を越える。「怒りのむこう側に突き抜け」*28たのである。同じように、ジグロは養父としては心に秘め続けたバルサへの恨みと憎しみをさらけだし、ヒョウルたちも憎しみをバルサにぶつけきった。
そして、「怒りにさらされて乾ききっていた砂地に、ぽつり、ぽつりと雨がふりはじめたように、なまあたたかい哀しみが、胸にあふれてきた」*29ように感じたバルサは、哀しみと苦しみとにうめきながらも、幼いバルサをしっかり包み込んでいきてきたジグロに対し、全てを越えて素直に向き合えるバルサへと変容を遂げたのであろう。
「バルサの、ジグロへの思いと、ジグロの、バルサへの思いとが、ぬくもりとなって……溶けあった」*30これは、本心をさらけだしたことによって、お互いの感情が初めて完全に解け合った瞬間であった。
バルサの心は「槍舞い」によって怒りのむこう側へ「突きぬけた」のである。そして、ジグロとヒョウルたちは、「清め」られ、あたたかい思いをもってこの世にわかれをつげることができたのである。それらは、ロスのいう「やすらぎと受容」の段階の訪れであるといえるだろう。そして、「槍舞い」がヒョウルの心を開き、弔いの儀式としての「槍舞い」が成功し、ジグロと直接心を向き合わせることによってバルサの「喪」の仕事もまた終わったのである。
7. 最後に
「槍舞い」とは、舞い手とヒョウル<闇の守り人>とが、無心に槍を振るい舞うことで、ヒョウルの心を開放し、心の奥底に押し込めたまま伝えられずに亡くなっていった本心を残された者たちに伝え、思いを清め、弔う儀式であった。
しかし今回の「槍舞い」においては、ヒョウルたちと同じように王によって人生を穢されたバルサが舞い手となることで、ヒョウルを清め弔うだけではなく、自らの「傷ついた心」をも「癒し」、ジグロと自分の人生を清めるための儀式となったのである。
<引用文献>
*1 上橋菜穂子著、『闇の守り人』偕成社(軽装版偕成社ポッシュ)、2006年 p.12
*2 上橋菜穂子著『天と地の守り人 第2部』偕成社ワンダーランド、2007年 p.181
*3 上橋菜穂子著『精霊の守り人』偕成社、1996年 p.230
*4 前出*3 p.226
*5 前出*3 p.230
*6 前出*1 p.111
*7 前出*1 p.174
*8 安島智子著「喪の箱庭表現」『臨床心理学大系 第17巻 心的外傷の臨床』金子書房、2000年、p.253
*9 前出*1 p.108
*10 エリザベス・キューブラー・ロス著、上野圭一訳『人生は廻る輪のように』角川文庫、2003年、p.283
*11 前出*1 p.289
*12 前出*2 p.165
*13~14 前出*1 p.359
*15~17 前出*1 p.340
*18~21 前出*1 p.341
*22~26 前出*1 p.342
*27~30 前出*1 p.343<参考文献>
石原千秋著、『大学生の論文執筆法』筑摩書房、2006年
上橋菜穂子著『精霊の守り人』偕成社、1996年
上橋菜穂子著『闇の守り人』偕成社(軽装版偕成社ポッシュ)、2006年
上橋菜穂子著『天と地の守り人 第2部』偕成社ワンダーランド、2007年
エリザベス・キューブラー・ロス著、上野圭一訳『人生は廻る輪のように』角川文庫、2003年
河合隼雄、空井健三、山中康弘編集『臨床心理学大系 第17巻 心的外傷の臨床』金子書房、2000年
ビヴァリー・ジェームス編著『心的外傷を受けた子どもの治療』誠信書房、2003年
まとめ
「児童サービス論」と聞くと、子ども向けに絵本の読み聞かせをしたりするイメージですが、実は深くて、テクスト論などを参考に読み込む必要があるものだと、この時に初めて知りました。
他の「児童サービス論」の課題では、「子ども向けのブックトーク原稿を作成する(テーマ、対象、ブックトーク開催時期、時間の条件付き)」というのもあって、難しいけれど楽しい学びをすることができました。
本の世界、幅広くて、奥深い。どんなルートも許される探検ができますね。
「児童サービス論」レポートの紹介でした。